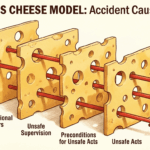2025/11/21
安全大会 挨拶の材料として、今回は、デミングさんの言葉を取り上げます。少し難しいですが、挨拶の材料としては良い角度ではないかと思います。
それではどうぞ。

「測定できないものは改善できない」
この言葉を、ピーター・ドラッカーの名言として耳にしたことがある方も多いでしょう。
しかし、実はこの言葉はドラッカーの著書には存在しません。
彼の考えに近い内容はあっても、
“Measurement”や“Improvement”を直接結びつけたこのフレーズは、後年になって誰かが作った要約や誤引用なのです。
そしてこの考え方に対して、真っ向から異を唱えた人物がいました。それが、W・エドワーズ・デミング博士です。
デミング博士とは
デミング博士は、アメリカの統計学者であり、品質管理と経営改善の第一人者です。
第二次世界大戦後の日本に招かれ、統計的品質管理(SQC)を日本企業に広めたことで、トヨタをはじめとする日本のものづくり文化に大きな影響を与えました。
日本で毎年授与されている「デミング賞」は、彼の名に由来しています。
そのデミング博士が残した有名な言葉があります。
> “It is wrong to suppose that if you can’t measure it, you can’t manage it.”
> (測定できないものは管理できないと考えるのは間違いである)
つまり博士は、「数字で測れないものの中にこそ、組織の本質がある」と説いたのです。
本サイトは安全大会の挨拶に焦点を当てていますので組織論は語りませんが、しかし、「数字で測れないもの」に注目することによって事故は減少させることができます。
建設現場における「測れない安全」
建設の現場では、災害件数、ヒヤリハット報告、KY活動の実施率、点検回数など、安全を「数字」で把握することが多くあります。もちろん、これは非常に大切です。数値化は、状況を見える化し、改善を進めるための基本です。
しかし、数字では見えない安全の要素が、現場にはたくさんあります。
- 朝礼で交わす「今日も気をつけような」の一言
- クレーンの合図を丁寧に確認し合う仕草
- 作業を止めて仲間の安全を優先する判断
- 若手に対して、ベテランが自然に声をかける姿
こうした“当たり前の行動”は、報告書には残りません。しかし、それこそが現場の安全文化をつくっています。数字に出ない「気づき」や「思いやり」が、事故を防ぐ最後の砦です。
測れないからこそ、感じる・話す・伝える
デミング博士の言葉を借りれば、安全管理とは「測ること」ではなく「理解しようとすること」。
現場で働く一人ひとりが、「今日はちょっと危ないな」「誰かが焦っているな」と感じ取る力こそ、数字以上の価値を持っています。そして、その感じたことを言葉にして伝え合う風土――これが「測定できないものを管理する」ための唯一の方法です。
数字の先に、人がいる
安全大会の場では、無事故日数や災害ゼロの報告など、成果を数字で共有することが多いと思います。
それは誇るべき成果です。けれど、今日ここで一つだけ強調したいのは、安全を守っているのは“人”であり、“数字”ではないということです。
安全は、機械や制度が自動的に生み出すものではありません。
「気を配る」「声をかける」「助け合う」――そうした“見えない行動”の積み重ねが、安全の本質です。
見えない努力を誇ろう
「測定できないものは管理できない」と考えてしまうと、人の心や行動といった最も大切な要素を見失います。
デミング博士の言葉を借りるなら、
> 「本当に重要なものの多くは、測定できない」
建設現場を支える安全も、まさにそうした“測れない価値”の上に成り立っています。
数字に表れない努力を互いに認め合い、見えない部分を感じ取れる現場――それが、真に強い安全文化を持つ職場ではないでしょうか。